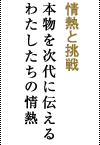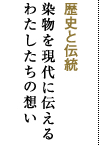![]()
江戸時代、伊達政宗は城下町をつくる際に、同じ職種による人々を集め、町人町を整備しました。仙台の染物職人は〈染師町〉の名で、「上染師町」(現/北目町から田町周辺)が、武士の着物や織物を中心に扱うのに対し、「南染師町」は、庶民の衣服や小物などを主に染めていました。
いまからおよそ300年前の享保年間(1716~1736)、初代「市左衛門」が広瀬川のほとりの堰場〈どうば〉(現/河原町・宮沢橋付近から国道4号線までの広瀬川周辺)と呼ばれる場所で、染物屋を起こしたのが武田染工場の始まりです。当時、染物には、きれいで大量の水が必要でした。明治27(1894)年には、11代「市左衛門」が、現在の南材木町(南染師町隣接)に工場を移転。昭和53(1978)年に株式会社となり、仙台における染物屋としての歴史をいまに伝えています。

|
〈インジゴ〉という色素を含む植物を使った「藍染(あいぞめ)」は、世界最古の染色法といわれています。日本においては、「藍染」は、濃紺の褐色(かちいろ=勝ち色)が、古く武家社会で愛好され、江戸時代には、その優れた防虫性や耐久性から、庶民の仕事着などで盛んに用いられ、「ジャパンブルー」と呼ばれました。 やがて、「藍染」より色落ちが少ない、化学染料による「硫化染め」が登場します。「硫化染め」は、濃紺、黒、茶といった幾つかの色に対応できる染色法でした。しかし、カラフルな発色に加え、手入れがしやすい「反応染め」がドイツで考案されると、それまで主流だった「硫化染め」に代わり、日本においても、昭和40年代からこの染色法が広く取り入れられるようになりました。現在ではさらに、シルクスクリーンなどの技法による、安価な「顔料染め」も加わり、伝統染色の「硫化染め」を行う染物屋は、数少なくなりました。 |
 |
 |
武田染工場では、昔ながらの染色法である「硫化染め」と「注染(ちゅうせん)」を中心とした、製品づくりを行っています。「硫化染め」は化学染料を使用し、「藍染」と同様に、布地を空気にさらして酸化させることで色を発色・定着させる染色法です。一方、明治時代、日本で開発された独自の染め技法とされる「注染(本染め)」は、仕上がりを想定した色の境目に、特殊な〈糊〉で土手をつくり、それぞれの染料を注いで模様を染める多色の型染め法です。「注染」は、ジャバラに重ねた30枚程度の生地の上から染料を注ぐため、従来に比べて生産性が一気に向上し、長年に渡り、日本文化の粋な庶民ファッションを支えてきました。これらの染色法は、いずれも布地の芯まで染料が浸透するため、表裏が無く、高級感あふれる美しい仕上がりになります。また「注染」では、ボカシ染めなどの微妙な表現も可能です。 武田染工場では、職人によるこの2つの伝統染色法にこだわり、現在は主に「手ぬぐい」や「帆前掛け」「袢纏」などを手掛けています。 |
|
伝統的な染色法で仕上げた染物は、現代の染色にはない本物ならではの、なめらかな生地の風合いや、色の奥行きが魅力です。また、ずっと使い続けることで色が程よく抜けて味わいが増し、使うひとそれぞれの生活に寄り添う、世界にひとつの愛着品になります。 例えば昔、手ぬぐいは、かさばらないうえ、伝統染色による優れた吸水性や吸湿性が、日本の蒸し暑い夏にも合う生活必需品として携帯されました。手ぬぐいの両端が切りっぱなしなのは、そこに水や汚れがたまらず衛生的なうえ、早く乾き、かつ手で簡単に裂いて、草履の鼻緒を直したり、怪我をした際の包帯に代用したりと、現代の防災用品の面からも注目できる、さまざまな用途で活用するための暮らしの知恵でした。 武田染工場では、この昔ながらの染物の利点と知恵を、その活用方法も含め、現代のライフスタイルのなかで〈生活必需品としての新しい価値〉として、皆様に提案していきたいと思っています。 |
 1961年、武田染工場の次男として誕生。東京の大学を卒業後、大手印刷会社へ就職。5年間、営業として大手飲料メーカーや外資系化粧品会社等を担当後、広告会社へ転職。大手鉄道会社の不動産事業、商社、ゼネコン等の広告業務を務め、2011年11月、現代表取締役に就任。 |